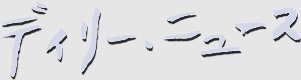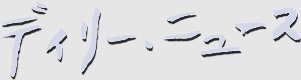|
「インターナショナル・コンペティション」
ビデオ作品解禁へ
今回からビデオ作品の応募も可能になった。山形12年の歴史の中で、大きな変更である。そのせいもあって、応募数も700本を超えた。ドキュメンタリー映画のスタッフ体制といえば、ぎりぎり小規模のものであったが、それでもフィルムの頃は数人のスタッフワークだった。それが、ビデオ作品になると、作家一人での制作というのが圧倒的だ。非常に個人的な切り口で、身近なところから広がりを持っている作品が多い。ただ、かつてのスケール感が薄れていっている気がする。ドキュメンタリー映画の今後の方向性は、当分はそちらに向かうだろう。
「アジア千波万波」
インターナショナル・コンペティションとの差はなくなった
「インターナショナル・コンペティション」がビデオ作品を解禁したことにより、「アジア千波万波」とのプログラムの考え方を見直す時期にきていると言える。映画祭'89 の、なぜアジアからのドキュメンタリー映画がないのか?という問い掛けから始まったこのプログラム。アジアの作家を育てるという小川紳介監督の志を継承してきた結果は、十分に実っている。もはやコンペとの差は無いといっていいほどだ。今年の傾向としては、社会性やテーマといった大上段に構えるのではなく、身近な個人の視点から社会が見えてくるような作品が多いことだろう。成熟した作品であると同時に、まだまだ若さと勢いのある作品ばかりで、コンペ以上の魅力に溢れている。
「日本パノラマ」
10年後を見据えて
「日本パノラマ」は1991年、第2回の本映画祭のスペシャルイベント、「日本映画パノラマ館」(企画運営YIDFFネットワーク、コーディネーター斎藤久雄)から、毎回形を変えながらも、その時々の日本のドキュメンタリー映画の今を表現し続けてきた。1991年のパノラマ館のサブカタログを見ると「21世紀の作家たちへ」とある。コーディネーターの斎藤久雄と数年前に何気なく話していて、当時の作品選考について聞いたことがあった。そのなかで「10年後も映画を撮っているであろう作家を選んだ」というのが印象的だった。この時紹介された作家達のほとんどが、いまだに映画、映像と関わりを持ち続けているのはたしかだろう。さらに言えば、現代の若い作家達の作品から、その影響を垣間見ることができる。初回のパノラマ館の凄さは、次の時代のことも見据えていたからに他ならない。
今回の私の関わった「日本パノラマ」もそうした継続性を念頭に置いた、作家性のしっかり感じられる作品を選んだ。また、他者に観せること、作家自身が外に向かおうとすること、自身の境界線からはみ出していこうという再生の意志を持ったものをプログラムしたつもりである。10年後にも彼らの新作に出会えることを期待しつつ。
「ネットワーク企画上映」
キナ臭い時代だからこそ忘れてはいけないこと
近頃なぜかチャールストンが流行っているという噂は聞かないが(岡本喜八監督作品を参照されたし)、米でのテロ事件以前から、日米共にタカ派的政治家がリーダーになった。バブルの後の強い指導力を求める傾向の結果なのだろう。そうした時代だからこそ、自国の歴史をきちんと認識することがより問われるのではないだろうか。特集1「大東亞戦争的記憶〜忘れられた人たち」は、そういう視点から作品を選んでみた。
また、特集2「山形を撮る」シリーズは山形でつくられた、あるいは山形を撮った作品を紹介している。「ネットワーク企画上映」は、これまで映画祭外の上映だったが、今回、正式に映画祭プログラムとなった。
|